高山社・藤岡の絹のあゆみ(年表)
| 西暦 | 和暦 | 事項 |
|---|---|---|
| 1684 | 貞享元年 | 「前橋風土記」に藤岡町の絹市の賑わいがみられる |
| 1827 | 文政10年 | 「諸国道中商人鑑」に藤岡の絹市が描かれる |
| 1830 | 文政13年 | 高山長五郎誕生 |
| 1831 | 天保2年 | 三井越後屋(三越)が諏訪神社に常夜燈1対を寄進する |
| 1848 | 嘉永元年 | 長五郎18歳で名主となる |
| 1850 | 嘉永3年 | 町田菊次郎誕生 |
| 1855 | 安政2年 | 長五郎が養蚕研究に取り組む |
| 1857 | 安政4年 | 三井越後屋(三越)が諏訪神社に手水石を寄進する |
| 1868 | 明治元年 | 長五郎が養蚕法「清温育」を確立したと伝えられる |
| 1873 | 明治6年 | 長五郎、養蚕改良高山組を組織する |
| 1875 | 明治8年 | 高山家の母屋(平屋部分)が建築と伝わる |
| 1877 | 明治10年 | 町田菊次郎授業員となる |
| 木村九蔵、養蚕改良競進組を組織する(明治17年に養蚕改良競進社と改名) | ||
| 上州新町紡績所が建設される | ||
| 1878 | 明治11年 | 長五郎「養蚕生法大略」を著す |
| 1879 | 明治12年 | 長五郎3ヶ村の連合戸長となる |
| 長五郎「養蚕法方略記」を著す | ||
| 高山家において第1回繭品評会を開催 | ||
| 1880 | 明治13年 | 吉井町において第2回繭品評会を開催 |
| 1881 | 明治14年 | 鬼石町において第3回繭品評会を開催(木村九蔵と連合して開催) |
| 1882 | 明治15年 | 町田家において第4回繭品評会を開催(木村九蔵と連合して開催) |
| 1883 | 明治16年 | (「清温飼」「清温育」の名称が資料に登場する) |
| 埼玉県児玉郡の私立繭共進会に出品し吉田埼玉県令より一等賞を授与される | ||
| 1884 | 明治17年 | 養蚕改良高山社と改称(社長高山長五郎) |
| 1885 | 明治18年 | 町田菊次郎副社長となる |
| 1886 | 明治19年 | 高山長五郎死去(享年56歳) |
| 社長に町田菊次郎、副社長に高橋茂太郎が就任 | ||
| 1887 | 明治20年 | 藤岡町に事務所と伝習所を移す |
| 副社長2名体制、新たに高山武十郎就任 | ||
| 1890 | 明治23年 | 町田菊次郎「高山社養蚕法案」を著す |
| 第3回内国勧業博覧会に蚕種・繭を出品 | ||
| 1891 | 明治24年 | 高山長五郎功徳碑を諏訪神社に建立 |
| 高山家の母屋兼蚕室(2階建部分)が建築される | ||
| 1895 | 明治28年 | 町田菊次郎講話「養蚕秘術」を出版 |
| 第4回内国勧業博覧会へ「高山社養蚕法案」並びに統計表を出品 | ||
| 1901 | 明治34年 |
私立甲種高山社蚕業学校開校 校長に町田菊次郎が就任 |
| 1907 | 明治40年 | 高山社で第2回共進会開催 |
| 1911 | 明治44年 | 高山社へ朝鮮実業団が訪れる |
| 1915 | 大正4年 | 町田菊次郎「最近養蚕法」を著し、天皇・皇后へ献上 |
| 1917 | 大正6年 | 町田菊次郎死去(享年66歳) |
| 1918 | 大正7年 | 高山長五郎生前の功績により従五位を贈られる |
| 1927 | 昭和2年 | 蚕業学校が廃校となる |
| 1928 | 昭和3年 | 蚕業学校の講堂が藤岡尋常高等小学校(現在の第一小学校)へ移築される |
| 1929 | 昭和4年 | 福島元七顕彰碑が富士浅間神社に建てられる |
| 1938 | 昭和13年 | 町田菊次郎頒徳碑諏訪神社に建立 |
| 1978 | 昭和53年 | 第一小学校移転に伴い講堂が解体される |
| 2007 | 平成19年 | 「富岡製糸場と絹産業遺産群」が世界遺産暫定一覧表に記載される |
| 2008 | 平成20年 | 高山社を考える会が発足 |
| 2009 | 平成21年 | 高山社跡が国史跡に指定される |
| 2010 | 平成22年 | 藤岡市が高山社跡を公有地化 |
| 2012 | 平成24年 | 日本政府が平成24年度の推薦候補とすることを正式に決定 |
| 2013 | 平成25年 | 群馬県がユネスコへ世界遺産登録推薦書を提出 |
| 2014 | 平成26年 | イコモスから世界遺産登録が適当と勧告される |
| 「富岡製糸場と絹産業遺産群」が世界文化遺産に登録される(6月25日) |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会文化財保護課文化財活用係
住所:〒375-0055群馬県藤岡市白石1291番地1
電話番号:0274-23-5997
ファクス番号:0274-22-6999
お問い合わせフォームはこちら





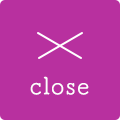
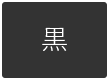
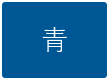
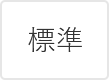
更新日:2025年06月13日