水道水の臭い(カビ臭)について
水道水の臭い(カビ臭)について
カビ臭の原因について
中央浄水場では神流川の表流水を利用して水道水をつくっています。9月下旬より水質検査で中央浄水場の原水と浄水からカビ臭の原因物質である「2-メチルイソボルネオール」が基準値内でありますが平常時より多く検出されています。
カビ臭物質は植物プランクトンなどの藍藻類(らんそうるい)が大量に繁殖すると産生することが知られており、水にカビ臭や墨汁臭、土臭をつけることがあります。
カビ臭対策について
中央浄水場では、カビ臭対策として、高品質活性炭を注入して、臭いを軽減する対応を実施しています。また、水質検査を定期的に行いカビ臭物質の変化を観察しています。
水質の安全性について
カビ臭の原因である「2-メチルイソボルネオール」は臭いの原因となりますが、毒性は認められておらず健康への影響はありません。また、水道水の使用には問題はありませんので安心してご利用ください。
カビ臭対象区域
藤岡地区、美土里地区、美九里地区、平井地区、下日野地区の一部(金井の一部)
神流地区の一部(上戸塚、下戸塚の一部、下栗須の一部)
小野地区の一部(上栗須、中栗須、中上、中下の一部)
参考 水道水質Q&Aより
〇カビ臭を感じる〇
湖沼、貯水池を水源としている場合、5月下旬から水温が上昇してくると、藍藻類等の微生物が盛んに繁殖し、水にカビや墨汁のような臭いをつけることがあります。これらの藍藻類等が体内で産生する2-メチルイソボルネオール、ジェオスミンが臭気物質として知られています。また、大雨による河川増水で河床の底泥が巻き上げられて、水にカビ臭や土臭をつけることもあります。活性炭による除臭処理が用いられますが、腐敗臭や病原菌のような不衛生なものではなく、河川や湖ならどこにでいる微生物が細胞内で産生した物質であり安全性に問題はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部浄水課
住所:〒375-0031群馬県藤岡市矢場1036番地
電話番号:0274-22-1205
ファクス番号:0274-22-1204
お問い合わせフォームはこちら





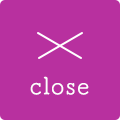
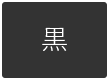
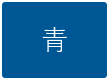
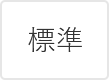
更新日:2025年10月31日