高額医療・高額介護合算療養費について
医療と介護サービスの両方を利用する世帯の負担を軽減するため、それぞれの年間の自己負担の合算額が一定の限度額を上回った場合、その額が支給されます。
医療保険と介護サービスの両方を利用する世帯の負担を軽減
医療費と介護サービス費のひと月ごとの自己負担額が規定の限度額を超えた場合、それぞれ、高額療養費・高額介護サービス費が支給されています。
これに加えて、同一世帯かつ同一医療保険に加入している単位で、医療費と介護サービス費の両方に負担がある場合、一定の基準を超える負担となった分を支給するという制度です。
計算期間内の世帯負担額を合算し、自己負担限度額を超えた分を支給
支給されるのは、同一世帯の中で国保に加入する人の医療費と介護サービス費のうち、計算期間内(8月1日~翌年7月31日)の自己負担額の合算が下記の表にある限度額を超えた場合です。住民票上で同じ世帯でも、加入している医療保険が異なるときは、別世帯となり合算できません。
また、限度額を超えた額が500円を上回る(支給額501円以上)場合のみが支給となり、合算の対象には、入院時の食事代や差額ベッド代などの保険対象外の負担した分や、高額療養費および高額介護サービス費として支給される額は含まれません。
なお、福祉医療受給者が本制度による支給を受けた場合、すでに支払い済みの福祉医療費の返還をお願いする場合があります。
| 所得区分 | 医療と介護の自己負担額 | ||
|---|---|---|---|
| 現役並み 所得者 |
現役並み3 | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
| 現役並み2 | 課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 | |
| 現役並み1 | 課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 | |
| 一般 | 現役並み所得者でなく、住民税非課税でない世帯 | 56万円 | |
| 低所得者2 | 住民税非課税世帯 | 31万円 | |
| 低所得者1 | 住民税非課税であり、所得が0円の世帯 「(注釈)」年金の所得控除を80万円として計算します |
19万円 | |
| 所得区分 | 医療と介護の 自己負担額 |
||
|---|---|---|---|
| 上位所得者 | ア | 所得が901万円超 | 212万円 |
| イ | 所得が600万円超901万円以下 | 141万円 | |
| 一般 | ウ | 所得が210万円超600万円以下 | 67万円 |
| エ | 所得が210万円以下 | 60万円 | |
| 非課税 | オ | 市町村民税非課税世帯 | 34万円 |
7月31日(基準日)に加入していた医療保険の窓口に申請
基準日に国民健康保険に加入していた人で該当する可能性のある人には、12月頃に支給申請書を郵送する予定となっていますが、計算期間内に医療保険者・介護保険者が変わった場合は自己負担額の把握ができないため申請書が届かない場合があります。該当と思われる人で通知が届かない場合はお問い合わせください。
また、申請後に合算計算をするため、申請された時点では支給になるとは限りません。後日、支給・不支給に関わらず、決定通知書をお送りします。
なお、後期高齢者医療保険や被用者保険(職場の健康保険)などに加入していた人も同じ制度があります。詳しくは加入している保険にお問い合わせください。
自己負担額証明書を事前に用意しなければならない人
計算期間内に医療保険者・介護保険者が変わった人は、以前の医療保険や介護保険での 「自己負担額証明書」が必要になりますので、事前に以前お住まいの市町村や、以前の医療保険から交付を受けてください。
被用者保険の人が申請する場合には、必ず介護保険の自己負担額証明書が必要となりますので、計算期間内に加入していたすべての介護保険者から自己負担額証明書の交付を受けてください。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
- 介護保険被保険者証
- 世帯主の預金通帳
- 介護サービス利用者の預金通帳
- 世帯主と被保険者のマイナンバーカード(「(注釈)」通知カードの場合は写真付きの身分証明書が必要です)
- 自己負担額証明書(「(注釈)」転入や他の医療保険に加入した期間がある人のみ必要です)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部保険年金課国保係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2822
ファクス番号:0274-24-6501
お問い合わせフォームはこちら





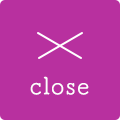
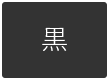
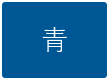
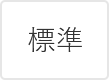
更新日:2024年12月02日