算額について
算額について
算額は、江戸時代から明治にかけて、人々が集まる神社や寺院を発表の場として算術の難問や解答を付けた絵馬のことです。このような風習は、算術の問題が解けたことに感謝して奉納されたと言われています。
平成9年(1997年)の調査によれば、全国に975面の算額が現存し、その中でも関東地方・東北地方が多く、群馬県は全国で4番目に多い80面がみることができます。奉納者の大半は関流の和算家で、このうち市内では5面が残され、もっとも古いものは天保2年(1831年)に奉納された立石神社の算額です。なお、東平井の秋葉神社に奉納されている算額は、関流和算家岸幸太郎が明治7年に奉納したもので、昭和46年4月16日に市の重要文化財に指定されています

秋葉神社の算額
「題意」

今、図のように円柱から黒積(長方形と菱形で挟まれた部分)を穿去(くりぬく)するものとする。円柱形(円柱の直径)、長(長方形の長い辺)、平(長方形の短い辺)を知って、黒面積(黒い部分の表面積)を求めよ。
市内の算額一覧表
| 奉納先 | 年号 | 西暦 | 住所 | 流派 | 問題数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立石神社 | 天保2年 | 1831年 | 立石乙1400 | 関流 | 2 |
| 龍源寺 | 明治6年 | 1873年 | 藤岡甲317 | 最上流 | 4 |
| 秋葉神社 | 明治7年 | 1874年 | 東平井1108 | 関流 | 5 |
| 金光寺 | 明治21年 | 1888年 | 藤岡甲62 | 関流 | 5 |
| 北野神社 | 明治24年 | 1891年 | 鮎川乙689 | 関流 | 5 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会生涯学習課
住所:〒375-0024群馬県藤岡市藤岡1485番地
電話番号:0274-22-6888
ファクス番号:0274-22-8738
お問い合わせフォームはこちら





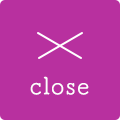
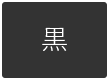
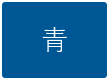
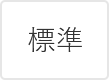
更新日:2025年03月04日