障害者差別解消法について
改正された障害者差別解消法が令和6年4月1日から施行されます
障害者差別解消法とは
この障害者差別解消法(「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)は、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目的とし、国や市区町村などの行政機関や会社、店舗などの民間事業者に対して、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」の禁止や「合理的配慮の提供」を求めて、その差別の解消に向けた取り組みを行っていくもので、平成28年4月1日から施行されています。
概要について
この法律では、主に次のことが定められています。
- 国の行政機関や地方公共団体等および民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
- 差別を解消するための取り組みについて、政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
- 行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応方針」を作成すること。
また、相談および紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。
不当な差別的取扱いとは
障害であることを理由に、正当な理由なくサービスの提供を拒否や制限をしたり、条件を付けたりするような行為のことをいいます。
|具体例(一例になります。)
- 障害があることを理由として一律に窓口対応を拒んだり、順序を後回しにする
- 障害があることを理由として言葉遣いや接客態度など接遇の質を下げる
- 付添いの方の同行を求めるなどの条件を付けたり、又は同行を拒む
合理的配慮とは
障害のある方からの求めに応じて、サービス等を利用するにあたって障壁となっている物事(社会的障壁と呼びます)を業務上過度な負担になりすぎない範囲で、取り除くための対応をすることです。
|具体例(一例になります。)
- 飲食店で車いす利用者がそのまま車いすに座ったまま利用できるよう、テーブルに備えてある椅子を片付けて、車椅子のスペースを確保する
- 聴覚障害のある方に筆談や手話などによる対話やわかりやすい表現を使って説明をする
- 視覚障害のある方に、説明書(板)やレストランのメニューなどの内容を読み上げる
社会的障壁(バリア)とは
障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で、障壁となるものを指します。
- 社会における事物(階段しかない入口など利用しにくい施設、設備)
- 制度(利用しにくい規則や制度、伴者を求める又は断る、電話のみの対応など)
- 慣行(障害のある方の存在を意識していない習慣、文化 音声ガイドのみなど)
- 観念(障害のある方への偏見など)
|具体例(一例になります)
- 道路や施設などで段差があって車いすが進めない
- 難しい漢字が多い、文章では、内容がわかりづらい
- 音声ガイダンスだけでは、情報が得ることができない
一部改正について(令和6年4月1日から施行)
改正の概要
- 事業者から障害のある方への「合理的配慮の提供」がこれまで「努力義務」でしたが、国や地方公共団体等と同様に「義務」になります。
- 国や地方公共団体の連携協力の責務および障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化(障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材の育成や情報・事例の収集、整理および提供に努めることに関する事項が追加されました。
| 行政機関 | 民間事業者 | |
|---|---|---|
| 不当な差別的取扱い | 禁止 | 禁止 |
| 合理的配慮の提供の義務化 | 義務 |
努力義務→義務 |
内閣府パンフレット


藤岡市では職員対応要領を定めています
藤岡市におきましても障害者差別解消法に基づき「藤岡市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定し、平成29年4月1日から施行しています。
- 藤岡市職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
障害者差別解消法の詳細
障害者差別解消法については、関係府省庁等において呼びかけられております。
内閣府ホームページでは、障害者差別解消法に関する資料を掲載しています。
国が策定した対応要領や内閣府の対応要領については、下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部福祉課障害福祉係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592
お問い合わせフォームはこちら





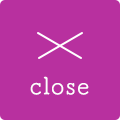
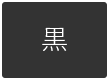
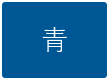
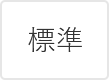
更新日:2024年03月18日